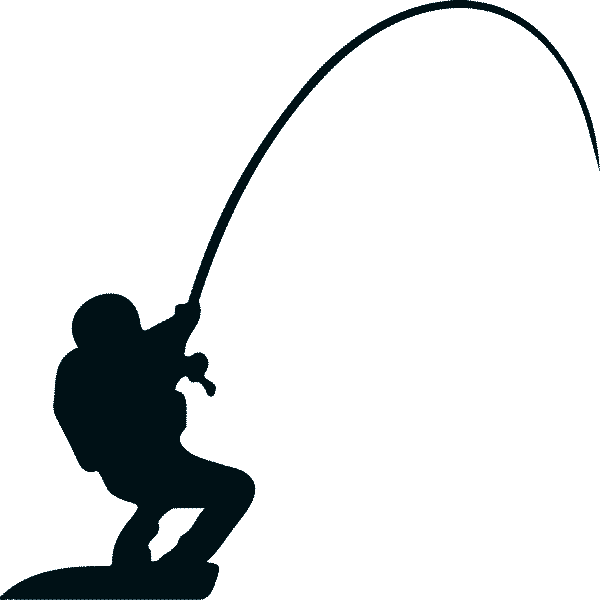穴子の刺身が少ない理由とは?毒の症状と締め方と血抜き

「穴子は刺身で食べれる?」釣り人や魚好きなら一度はそう疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。
スーパーや鮮魚店では滅多に見かけない“アナゴの刺身”。
実はその裏には、ただの流通や需要の問題ではない、しっかりとした理由が隠れています。
この記事では、「なぜアナゴの刺身は珍しいのか?」という疑問に対して、毒の有無やその症状、安全に食べるための締め方や血抜きの方法を、釣り人の視点からわかりやすく解説していきます。
アナゴの刺身の魅力と、その裏にある注意点を知ることで、釣った魚をより深く楽しむヒントが見つかるはずです。
そもそも「穴子」とは?どんな魚なの?刺身が少ない理由

穴子とは、ウナギのような細長い体形をした夜行性の海水魚で、日本では「マアナゴ」が一般的です。
東京湾や瀬戸内海などで釣りや漁業の対象となっており、調理法によっては非常に美味。
普段目にする煮穴子の陰には、活け締めや処理の技術によって生まれる“本物の旨さ”があるのです。
 生態と特徴
生態と特徴

マアナゴは、ウナギ目アナゴ科に属する海水魚です。
名前の由来は、“穴に棲む魚”という意味から来ているとされています。
昼間は岩や砂泥の“穴”に潜み、夜になると活動するという生態に由来しています。
| 体長 | メスは1mまで大きくなるオスは40cm |
|---|---|
| 体色 | 茶褐色 |
| 生息域 | 沿岸砂泥底 |
| 食性 | 肉食性 |
| 特徴 | 体側に白い斑点 |
| 漢字 | 真穴子 |
| 地方名 | ハカリメ、ホシアナゴ、キンリョウメ など |
 刺身が少ない理由とは?
刺身が少ない理由とは?

穴子の刺身が市場に少ない主な理由は、血液に含まれる血清毒素(イクチオヘモトキシン)の存在です。
この毒素は適切な処理をしなければ食中毒を引き起こす可能性があり、通常の流通では生食用の処理が困難なため、加熱調理用として販売されているのが現状です。
この毒素はタンパク質であるため、60℃で5分の加熱で失活します。そのため、天ぷらや煮穴子などの加熱調理では安全に食べることができます。
厚生労働省:魚の自然毒 血清毒 毒の症状
毒の症状

穴子の血液には「イクチオヘモトキシン」というタンパク質の血清毒が含まれています。
この毒素を摂取すると、下痢や吐き気などの中毒症状を、目などの粘膜に入ると結膜炎や激しい炎症を引き起こします。
穴子の毒は、フグ毒のように非常に強いものではありませんが、油断は禁物です。
釣った「穴子」の持ち帰り方・締め方と血抜き

釣れた穴子を美味しく、かつ安全に食べるためには釣った直後に「活締め」と「血抜き」を確実に行うことが非常に重要です。
これにより、鮮度を保ち、身の臭みや毒性リスクを減らすことができます。
釣れた穴子は締めた後、海水でしっかりと血抜きを行うことが美味しく安全に持ち帰るための基本です。
 締め方・血抜き
締め方・血抜き

釣れた穴子の締めと血抜きは、美味しく安全に食べるための重要な工程です。
中骨の切断による締めと、海水を使った丁寧な血抜きを確実に行いましょう。
可能であればヌメリ取りも行うことで、調理の手間を省けます。これらの処理を適切に行うことで、鮮度を保ち、臭みを抑え、安心して穴子料理を楽しむことができるでしょう。
アナゴの刺身
野食ハンター茸本朗様
 ぬめり取り
ぬめり取り

穴子のぬめり取りには酢が極めて効果的です。酢の酸性(pH約2.5)がぬめりの成分を凝固し、同時に臭みの原因となる成分も除去します。
酢に浸すことでヌメリが白く変色し浮き上がります。
これを、包丁でこそげ取っていきます。ヒレ周りや頭も丁寧にこそげ取っていきます。
 生で食べられる?
生で食べられる?

釣ったアナゴを生で食べることは、毒性や食中毒のリスクがあるため、基本的に避けるべきです。
アナゴに含まれる毒素は加熱によって無毒化されるため、蒲焼きや天ぷらなど、加熱調理して美味しくいただくのが安全で一般的な方法です。
特別な処理を施したアナゴの刺身を提供する店もありますが、一般の釣り人が安易に生食することは非常に危険であることを理解しておきましょう。
穴子の刺身が少ない理由とは?毒の症状と締め方と血抜き まとめ

釣り好きの皆さんなら、一度は釣ってみたいと思う魚、穴子。
天ぷらや蒲焼きなど、加熱調理で美味しくいただける魚ですが、刺身で食べるのはあまり一般的ではありません。
実はこれには、毒のリスクと処理の難しさという大きな理由があるのです。
この毒素は熱に弱く、60℃以上で5分以上加熱すれば無毒化されます。
そのため、蒲焼きや煮穴子などの加熱調理が一般的なのです。
未処理の生のまま摂取すると嘔吐・下痢・腹痛などの軽い食中毒症状を引き起こす可能性があります。
釣った穴子を生で食べることは、毒性や食中毒のリスクがあるため、基本的に避けるべきです。
とはいえ、釣り人にとっては「自分で釣った新鮮な穴子を刺身で食べてみたい」という欲求もあるはず。
その場合は、リスクを理解したうえで、自己責任での徹底処理が前提です。
適切な処理を経た穴子の刺身は、上品な甘みと繊細な食感が特徴で、「白身魚の最高峰」と評する人もいるほどの味わいです。
市場に流通しないためこそ、釣り人だけが味わえる貴重な体験と言えるでしょう。
とはいえ、生食には必ずリスクがあることを忘れてはなりません。釣った穴子を美味しく、安全に楽しむには、正しい知識と丁寧な処理が釣り人の責任です。
穴子の刺身が少ない理由とは?毒の症状と締め方と血抜き FAQ
Copyright © AZU. All rights reserved.