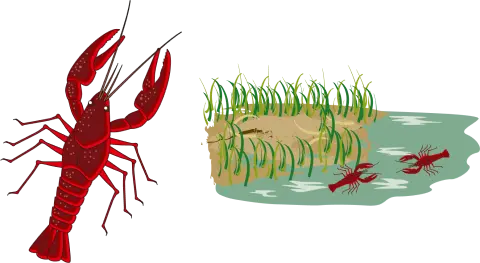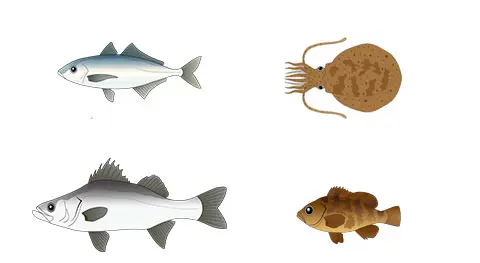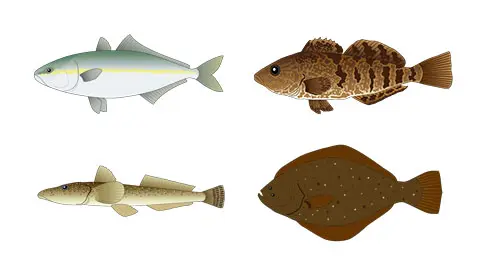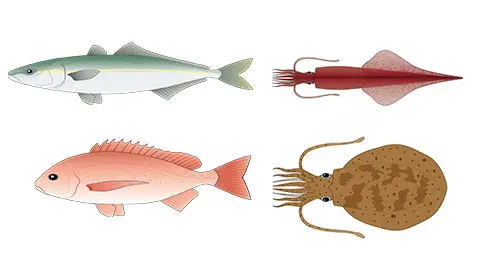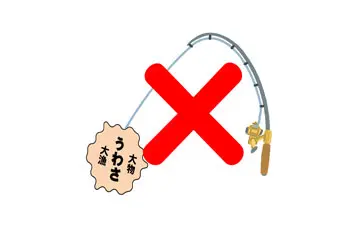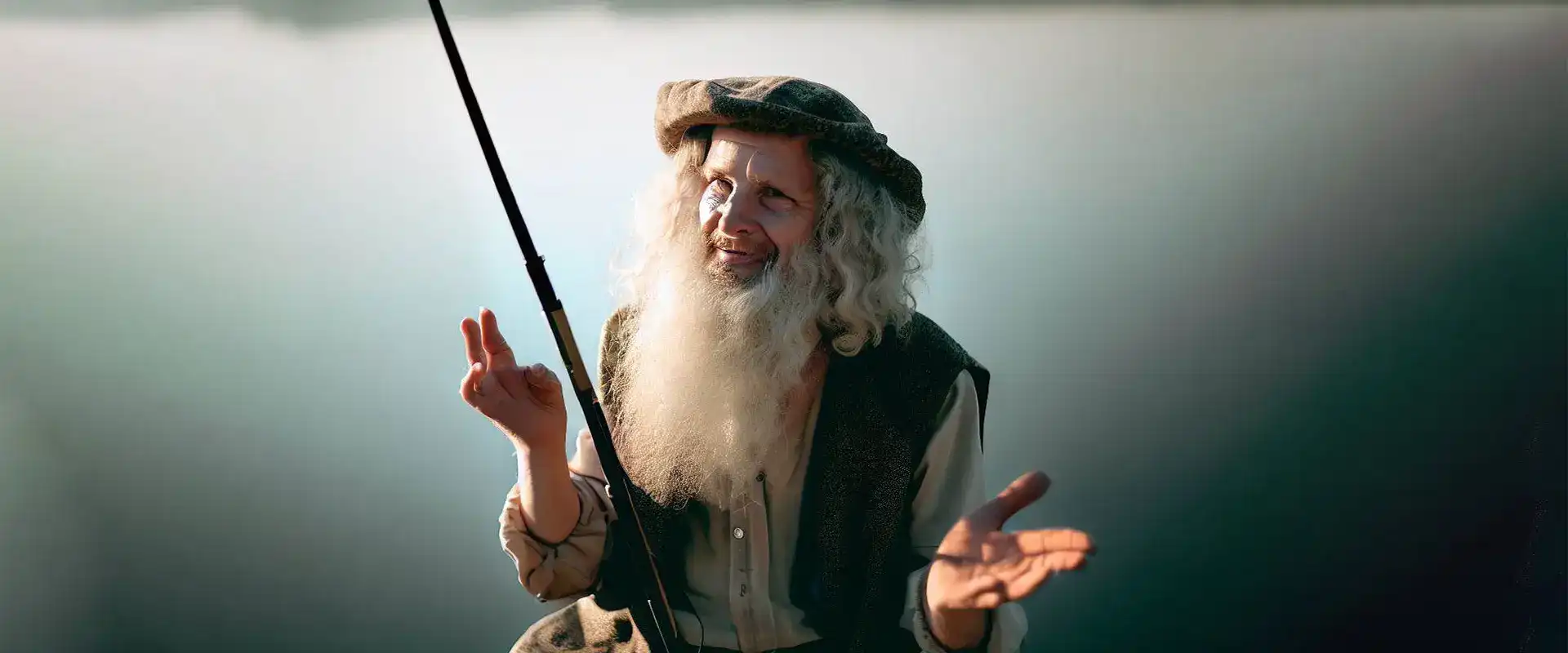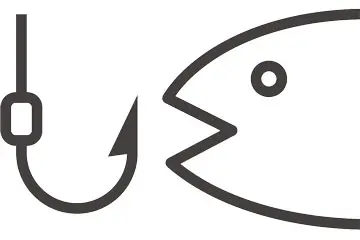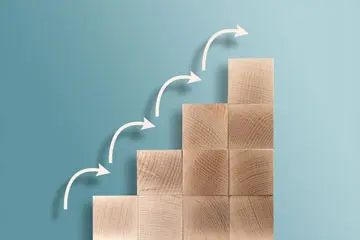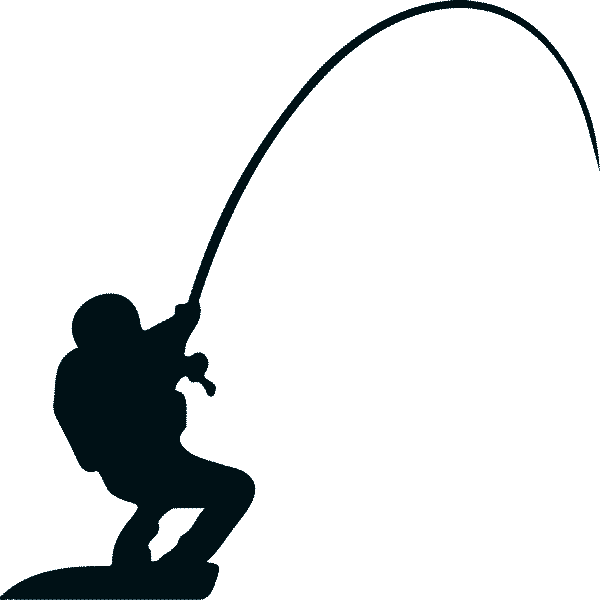釣りの魅力を知ったのは、子供の頃。近くの池や川でザリガニやハエジャコを釣るのが楽しみでした。
釣りは、自然と触れ合う素晴らしい趣味だと感じました。
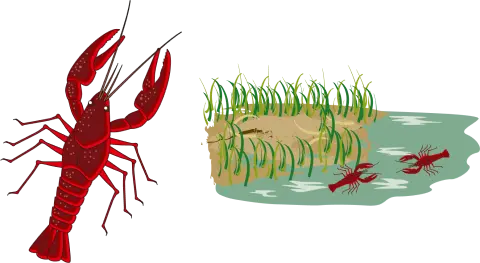 野池のザリガニ
野池のザリガニ
渓流や野池、釣り堀など、様々な場所で釣りを楽しみました。
仕掛けの違いや、エサの種類、道具の使い方など釣りの基本を学びました。
 様々な釣り
様々な釣り
中学生の頃には、ルアー釣りに夢中になり、ブラックバスを熱心に追い求めるようになりました。
しかしながら、学生時代は忙しさにかまけて釣りから遠ざかりましたが、社会人になって再びバス釣りに熱中。
船舶免許も取得し、ボートでの釣りも経験しました。
 ボートでバス釣り
ボートでバス釣り
その後、釣り場を海へ移し、ライトなルアー釣りを楽しむようになりました。
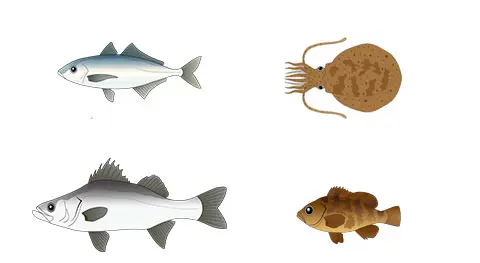 ライトなルアー釣り
ライトなルアー釣り
狙う魚種も増えて磯場や、サーフなど季節に応じて多彩な釣りを楽しんできました。
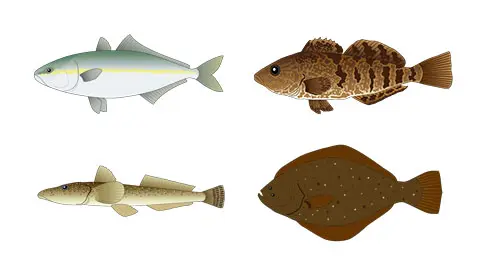 磯場やサーフの釣り
磯場やサーフの釣り
30代後半からは、オフショアの釣りにも挑戦。海釣りの魅力を心ゆくまで味わいました。
- ジギング
- タイラバ
- ティップラン
- イカメタル など
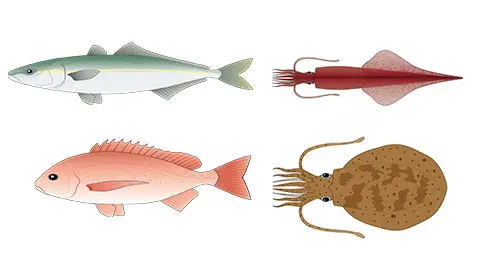 オフショアの釣り
オフショアの釣り
現在は主に、自分の好きなイカ釣りに集中しています。
釣りは自分らしく楽しめる最高の趣味だと思っています。
 アオリのバイトイメージ
アオリのバイトイメージ
この記事では、私自身の視点から、これまでの釣りに関する経験と知識を共有しました。
ささやかながらも、皆さまにとって「素敵なフィッシングライフ」のお手伝いができれば幸いです。
近畿釣り情報「hiro」